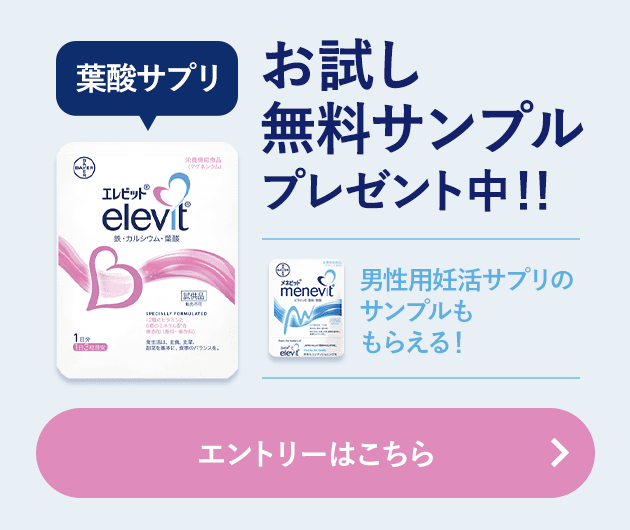トップ>妊活TOP>妊活中に知っておきたいこと>妊活の「こころとからだ」に関するコラム> 子作りを考える人の妊活はじめてガイド。タイミング法とは?
【医師監修】子作りを考える人の妊活はじめてガイド。タイミング法とは?
赤ちゃんが欲しいと思って妊活を始めたら、まず、なにから試そうと考えるでしょうか。タイミング法という言葉をよく聞くから、自己流でまずはやってみようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
不妊治療としてよく知られているものには人工授精や体外受精などがありますが、タイミング法も不妊治療のひとつです。今回は自己流でタイミングを合わせる方法より妊娠しやすい方法として、産婦人科で行うタイミング法についてご紹介します。
タイミング法とは?
タイミング法とは、不妊治療のひとつであり、性交のタイミングを排卵時期に合わせることで、妊娠の確率を高める方法です。タイミング法は、不妊治療の中でも最初に行われることが多い治療法です。医師の診察を受け、さまざまな検査を行って排卵日を予測してもらい、医師から指示を受けた日に性交を行います。
妊娠しやすいタイミングと回数
妊娠しやすいタイミングは、予測された排卵日を基準に考えます。
排卵する1~2日前が最も妊娠しやすいとされており、排卵する6日以上前と排卵日の翌日以降は、ほぼ妊娠しないという研究報告があります。
また、排卵された卵子の寿命は約24時間であるのに対して、女性の体内に入った精子の寿命は約72時間と長生きです。そのため、排卵日より前に性交したほうが、妊娠の可能性が上がると考えられます。
米国生殖医学会は、排卵日の4日前から排卵日前日までに、1〜2日おきの性交が妊娠しやすいとしています。こうしたことから、妊娠しやすいタイミングは排卵日の4日前~1日前で、回数は2~4回程度と考えられます。
排卵日の予測方法は?
排卵日を予測する方法はいくつかあり、病院ではそれらを併用して排卵日の予測を行います。主な排卵日の予測方法をご紹介します。
基礎体温
基礎体温とは、眠ったあと目覚めたときに、起き上がらず寝たままの状態で舌の下に婦人体温計を入れて測った体温のことです。女性は月経がはじまると体温が低くなり、排卵後から次の月経までは体温が高くなります。低体温の最終日や、高温期前に体温が急に下がる日が排卵日である可能性が高いことから、低温期から高温期に変わる前後あたりが排卵日だと予測することができます。
経腟超音波断層法
排卵日より前に病院を受診して、経腟超音波検査(内診台で受けるエコー検査)で卵胞(卵子の入った袋)の大きさを測定し、その大きさによって、排卵日を予測します。
頸管粘液
子宮頸管(しきゅうけいかん:子宮の入り口で膣につながっている部分)でできる頸管粘液(けいかんねんえき)の様子で受精可能日を予測します。排卵直前になると、粘液の量が増えて、白またはクリーム色となり、膣もしっとり潤った感じになります。
尿中血中LH検査
排卵期になるとLH(黄体形成ホルモン)が多く分泌されることから、尿中や血中のLHの値の変化を知ることで、排卵日が予測できます。
病院でタイミング法の指導を受けましょう
まずは自分たちで基礎体温を測ってタイミングを取ってみるのもいいでしょう。しかし、排卵日はちょっとした体調の変化でも変わってしまうことがあります。排卵日を正確に予測するためには、複合的に判断する必要があるため早めに専門の医師に相談してみましょう。
この記事は2021年9月14日時点の情報です。
Last Updated : 2022/Apr/5 | CH-20220328-12